- 「薄毛が気になってきたけど、髪の毛に必要な栄養が足りてないのかな…」
- 「髪の毛には栄養が必要って聞いたけど、どんな栄養素が必要なんだろう…」
この記事を読まれている方は、こんな悩みを抱えているのではないでしょうか。
そこで本記事では髪の毛に必要な栄養素について解説いたします。摂取量の目安や具体的な食べ物についても解説していますので、ぜひ最後までお目通し下さい。
目次
髪の毛は主にタンパク質から作られている
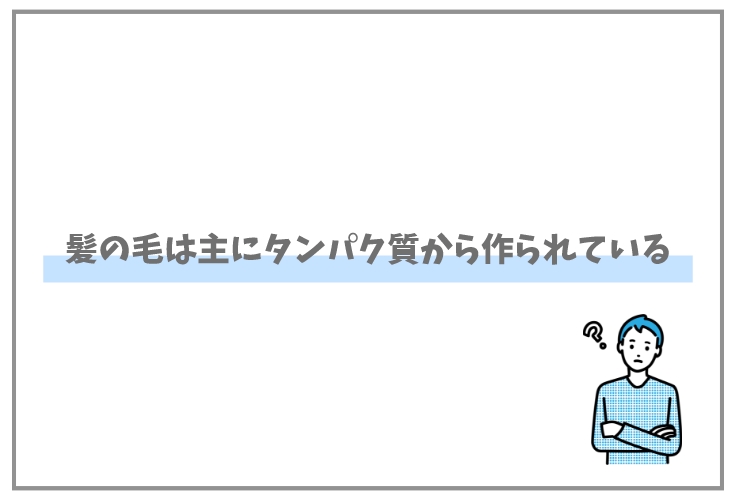
髪の毛の大部分は18種類のアミノ酸から合成されたケラチンというタンパク質から生成されています。
そのためアミノ酸を豊富に含んだタンパク質を摂取することが、髪の成長にとって大前提必要な栄養であると言えますが、タンパク質だけ摂れば十分という訳ではありません。
ケラチンを合成する際には亜鉛やチロシンが必要であり、良い頭皮環境を保つためにはビタミン群などの栄養素もかかせません。
主成分こそタンパク質であるものの、髪の毛が形成される過程で多くの栄養素が必要となるのです。
栄養不足になると髪はどうなるのか
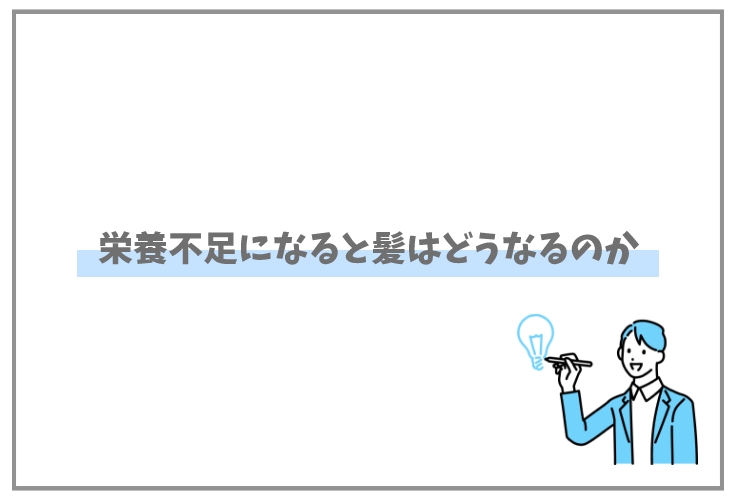
髪の毛を形成する際に必要な栄養素が十分に摂れていないと、髪の毛は十分に成長し切れずに、細くハリやコシの無い髪になってしまい、薄毛の原因となることもあります。
髪の毛は生命維持に関係の無い部分のため、体内に取り入れた栄養素が使われる優先度も低く、一番最後。そのため、きちんと栄養を摂ることが髪の成長ひいては薄毛対策に重要なのです。
髪の毛の成長に摂るべき栄養素と食べ物
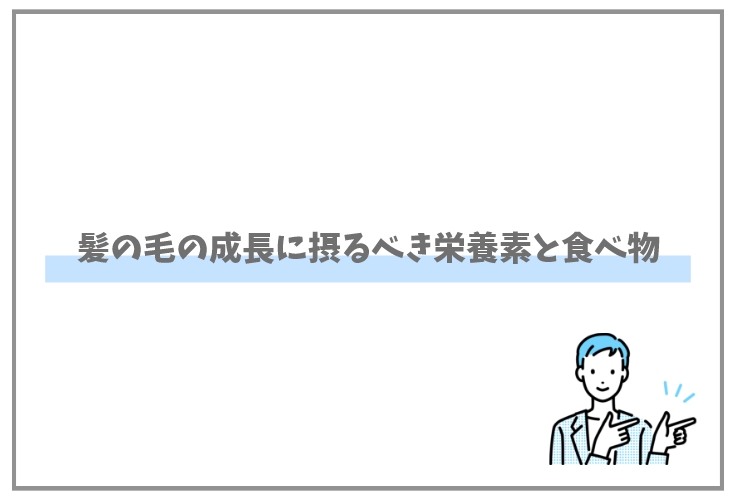
髪の毛の成長のために摂るべき栄養素は様々ですが、中でも重要な以下4つの栄養素をご紹介します。
- 良質なタンパク質
- 亜鉛
- ヨウ素
- ビタミンA
- ビタミンB6
- ビタミンE
これらが含まれている食べ物を含め、それぞれ詳しく解説していきます。
良質なタンパク質
髪の毛の成長には、基となる良質なタンパク質の摂取がかかせません。ここでいう良質なタンパク質というのは、必須アミノ酸がバランス良く含まれたタンパク質のことを指します。
同じタンパク質でもアミノ酸のバランスや含有量は異なる
タンパク質は複数のアミノ酸から形成されていますが、食べ物によってアミノ酸の配合バランスや量は異なり、アミノ酸のバランスや量に偏りがある食材も存在します。
良質なタンパク質かどうか判断するには「アミノ酸スコア」を見る
では、どのように良質なタンパク質かどうかを判断するかと言えば「アミノ酸スコア」と呼ばれる指標を用います。
アミノ酸スコアはFAO(国際連合食糧農業機関)やWHO(世界保健機関)、UNU(国連大学)が提案している食品に含まれるアミノ酸の量やバランスを定量化したもの。日本では文部科学省が各食品のアミノ酸スコアを公開しています。
アミノ酸スコアの高い食品
アミノ酸スコアが高く、多くのタンパク質を含む食品としては、以下のような食品が挙げられます。
| 食べ物 | アミノ酸スコア |
|---|---|
| 鶏肉(もも皮つき 生) | 100 |
| 鶏肝臓(生) | 100 |
| 豚肉(ロース 脂身つき 生) | 100 |
| 真アジ(皮付き 生) | 100 |
| シロサケ(生) | 100 |
| カキ(養殖 生) | 100 |
普段の食事から栄養を摂ることが難しい場合には、プロテインも活用してみると良いでしょう。
プロテインと聞くとトレーニングをしている人だけが飲むもののように感じますが、プロテインはタンパク質の摂取を目的としたものであり、トレーニングをしていない方が飲んでも問題ありません。
また、タンパク質は十分に取れているもののアミノ酸が取れているか不安という方はEAAと呼ばれる必須アミノ酸が含まれたサプリメントもオススメです。
亜鉛
亜鉛は髪の基となるケラチンの合成に必要な栄養素です。体内では生成できない栄養素のため、食事やサプリメントから摂取する必要があります。
また、亜鉛はAGAの原因である男性ホルモン「DHT(ジヒドロテストステロン)」の基となる5αリダクターゼと呼ばれる還元酵素の活動を阻害する働きも持っています。
一日の摂取目安量
亜鉛の一日の摂取目安量は以下の通りです。(男性の場合におけるデータ)
| 年齢 | 摂取目安量(mg/日) |
|---|---|
| 18歳~29歳 | 11g |
| 30歳~49歳 | 11 |
| 50歳~64歳 | 11 |
| 65歳~74歳 | 11 |
| 75歳以上 | 10 |
多く含まれている食べ物
亜鉛が多く含まれている食べ物としては、以下が挙げられます。
- 牡蠣
- イワシ
- しらす干し
- 豚肉
- 牛肉
- 海苔
肉類にも豊富に含まれているため、ほとんどの方は意識的に摂ろうとしなくても十分に栄養が摂れている可能性は高いでしょう。
ヨウ素
ヨウ素とは昆布やわかめなどに豊富に含まれる海洋性のミネラルです。ヨウ素は甲状腺ホルモンと呼ばれる体全体の新陳代謝を調整する役割を持つホルモンを生成する効果があります。
このホルモンはタンパク質の合成を促進するため、髪の毛の成長にはかかせません。
一日の摂取目安量
環境省の発表によれば、1日の摂取目安量は
- 推定平均必要量が0.0095mg
- 推奨量が0.13mg
とされています。推奨量でも0.13mgとかなり少ない量のため、何らかの海藻類を摂取すれば十分にクリアできるでしょう。
多く含まれている食べ物
ヨウ素が多く含まれている食べ物としては、以下が挙げられます。
- 昆布
- ひじき
- わかめ
- 海苔
いずれも数グラムを摂取すれば簡単に推奨量を超えることができます。
ビタミンA
ビタミンAは皮膚の健康に関わる栄養素です。主に皮膚のターンオーバーを促進させる効果があります。
私たちの肌はターンオーバーによって一定の周期で生まれ変わり、健康を維持しています。ビタミンAが不足するとターンオーバーが乱れてしまい、その結果、頭皮環境が荒れて髪の毛に悪影響を与えます。
こういった背景があることから、髪の毛にとってもビタミンAは大事な栄養素と言えるでしょう。
一日の摂取目安量
ビタミンAの一日の摂取目安量は以下の通りです。(男性の場合におけるデータ)
| 年齢 | 摂取目安量(㎍RAE/日) |
|---|---|
| 18歳~29歳 | 850 |
| 30歳~49歳 | 900 |
| 50歳~64歳 | 900 |
| 65歳~74歳 | 850 |
| 75歳以上 | 800 |
多く含まれている食べ物
ビタミンAが多く含まれている食べ物としては、以下が挙げられます。
- 豚肉
- 鶏肉
- 牛肉
- うなぎ
- バター
- 海苔
- シソ
ビタミンB6
ビタミンBには多くの種類がある中、ビタミンB6はアミノ酸の代謝を助ける働きがありケラチンの合成に関係しています。
また、皮膚のバリア機能を維持するためにも必要な栄養素のため、頭皮環境を健康に保つためにも必要な栄養素です。
一日の摂取目安量
ビタミンAの一日の摂取目安量は以下の通りです。(男性の場合におけるデータ)
| 年齢 | 摂取目安量(mg/日) |
|---|---|
| 18歳~29歳 | 1.4 |
| 30歳~49歳 | 1.4 |
| 50歳~64歳 | 1.4 |
| 65歳~74歳 | 1.4 |
| 75歳以上 | 1.4 |
多く含まれている食べ物
ビタミンB6が多く含まれている食べ物としては、以下が挙げられます。
- ししとう
- かつお
- ブロッコリー
- ゴマ
- 落花生
ビタミンE
ビタミンEは血行促進効果を持ったビタミン。髪の毛の栄養は血によって頭皮へと運ばれてくるため、血行促進効果のあるビタミンEを摂取することで、髪の毛に十分な栄養が行き渡りやすくなります。
生活習慣の乱れや偏った食生活によって血行不良に陥りがちやすい現代においては、積極的に摂りたい栄養素の一つです。
一日の摂取目安量
ビタミンEの一日の摂取目安量は以下の通りです。(男性の場合におけるデータ)
| 年齢 | 摂取目安量(mg/日) |
|---|---|
| 18歳~29歳 | 6.0 |
| 30歳~49歳 | 6.0 |
| 50歳~64歳 | 7.0 |
| 65歳~74歳 | 7.0 |
| 75歳以上 | 6.5 |
多く含まれている食べ物
ビタミンEが多く含まれている食べ物としては、以下が挙げられます。
- アーモンド
- 落花生
- オリーブオイル
ビタミンEを多く含んでいる食べ物は限られる上、肉魚や米などの主食にはほとんど含まれていないため、サプリメントなどで摂取することをオススメします。
髪の毛に関するよくある質問
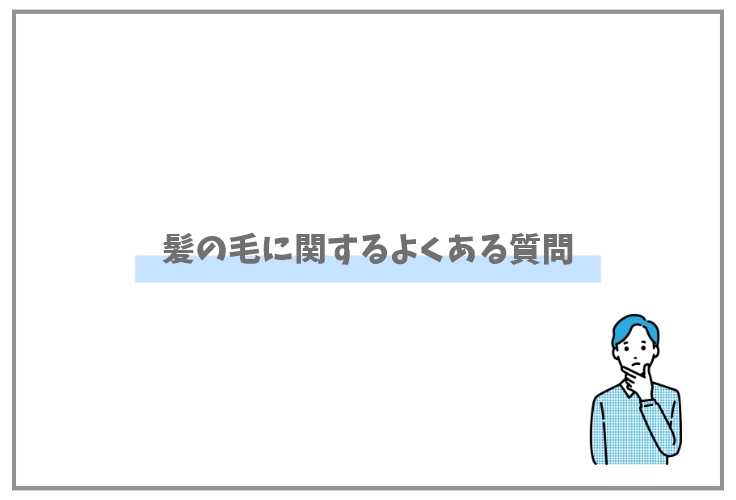
最後に髪の毛に関するよくある質問についてまとめて回答いたしました。
Q. サプリメントで栄養を摂取しても問題ありませんか?
サプリメントで栄養を摂取しても問題はありません。しかしサプリメントを使用する際には過剰摂取に気をつけましょう。
栄養素には耐用上限量と呼ばれる摂取の上限が定められていることがあり、その上限を超えて摂取することで健康被害が生じる可能性があります。
そのため、記載の摂取量は必ず守った上、サプリメントに頼りすぎないようにしましょう。
Q. シャンプーを使って頭皮に栄養を与えることはできますか?
角質層までであれば頭皮に栄養を与えることはできると言えます。しかし、角質層というのは肌の一番表面であるため、経口摂取と比べた際の効果は微々たるものと言えるでしょう。
まとめ
今回は髪の毛に必要な栄養素について解説させていただきました。本記事で重要なポイントは以下の3つです。
- 髪の毛のほとんどは18種類のアミノ酸が合成したタンパク質で作られている
- 栄養不足になると薄毛の原因にもなる
- 髪の毛に必要な栄養素は良質なタンパク質・亜鉛・ヨウ素・ビタミンA・ビタミンB6・ビタミンE
普段の食生活を今一度見直して、献立を作ってみてはいかがでしょうか。
